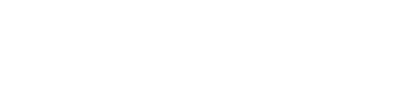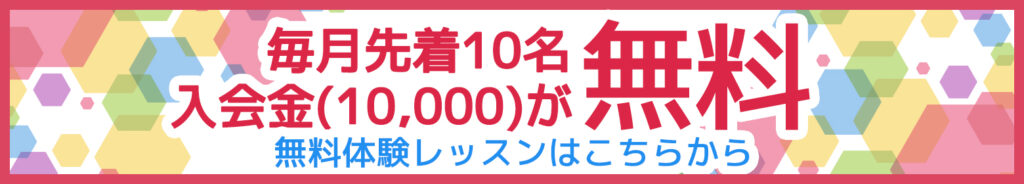ボーカルレコーディングの仕事をしていると、ボイストレーニングなど一切うけた経験がないのに、驚くほど歌が上手な人っています。
「才能」と言ってしまえばそれまでですが、多く出会っているうちに、この種類の人たちの傾向がわかってきましたので、紹介したいと思います。
これらの傾向を踏まえて自分の学び方を見直せば、その要素を自分のトレーニングに活かせるかもしれません。
普段から声が大きく、抜けがいい
普段声が大きい人って、最初から腹式呼吸ができている場合がほとんどです。
大きい声を出すには呼吸量を増やさなければならず、それを長時間継続するには喉に不要な力みがないことが必要です。
これを日常的に行なっている人は「呼吸を大きくつかっても力まない喉」という超絶有利な初期ステータスをもっています。
これですでに呼吸と喉の扱い方はクリアなので、あとは発声法とかコントロールを学べば基礎発声のフェーズはクリアです。
うーん、なんてチート(笑)
普段の声を改善する、というアプローチはトレーニングとしてもとてもオススメです。
「大きい声出して喉絞めない」でOKです。
喉の力みがあると、すぐ喉が枯れますので、喉が枯れない大きい声の出し方を学んでください。
ピアノ、ダンス経験者
ピアノ経験者はとにかく音感が強いことが多いです。
「楽譜を演奏する」という考え方で歌にアプローチできるので、レコーディングをしていても話がしやすく、シーケンスの問題を解決するまでのスピードが違います。
歌はまず、ピアノの音階に対しての聴音とチューニングを合わせることが重要なんで、調律されたピアノを多く聞いているだけでピッチは良くなりやすいです。
ダンス経験者は「体をつかってリズムをとる」ができているので、リズム感がよくグルーブへの理解が無意識的にできています。
「体全体をつかって声を出す」という意識がもてると、肩から上への不要な力みが減りやすくなるのでおすすめです。
ピッチやリズムに課題がある人は、練習用の鍵盤とメトロノームを用意することは必須です。
ピッチやリズムが安定すると、不安な要素が減ることで表現や体全体の力みも減り、リラックスした自然なニュアンスが出るようになりますよ。
とにかくたくさん聴く
表現力が高い人、いわゆる演出技術が高い人は「同じ曲をたくさん聴いて特徴を感覚的にとらえる」癖がついています。
この「記憶」ではなく「感覚的に理解する」という考え方って、歌のような反射神経が大事なジャンルにとってとっても大切です。
理解するには頭での学習が向いていますが、技術を自由自在に使うには「無意識にできるまで繰り返す」練習方法がもっとも向いています。
マスターしたい曲があれば、とりあえず楽曲をループで200回くらい聴きましょう。
飽きてもなんでも、繰り返し聴いてください。
そのうち、音楽を再生してなくても、頭の中でその音楽を流せるようになります。
確認しなくても頭の中で歌のイメージを再生できるので、ニュアンスの模倣がとっても楽になります。
こうやって学んでいる人の方が、細かく歌のニュアンスをトレースできているので、コピーがめちゃくちゃ楽になります。
繰り返し聴きながら歌をあわせてみると、その誤差にも気づけるので、ループ再生しながら練習する方法は、ニュアンスや表現の模写には最も適している方法だと思います。
これができたら、カラオケを流さずメトロノームにあわせて同じように歌えれば完璧です。
他のジャンルにも柔軟に興味をもてる
例えば、絵を描くこと、料理を作ること、Youtuberをやっている、など他のジャンルの活動も並行して行なっている人は、コツをつかむのが上手です。
技術の習得方法って、どのジャンルも似ている部分があるので、何をすれば効率よく練習できるのか、というポイントをおさえることができます。
特定のジャンルでしか活動しない人は、自分のこだわっているポイントに必要以上に固執してしまったりバランスが悪くなります。
表現してつたえる、という作業は色々なジャンルに同じようにあるので、他のジャンルからヒントを得ることは客観性を持つという観点でも効果的です。
わりきりがいい
上手い人ほど、レコーディングはあっさり短時間で終わります。
上手なんだから当たり前じゃないかって?そんなことありません。
技術があるのに細かいポイントが気になって、何度もリテイクを重ねて喉が消耗。
何がしたいのかわからなくなってパニック、っていうパターン、っけこうあります。
ボーカルレコーディングは「声」が命です。
不要にリテイクを重ねれば、時間がたつほど喉のコンディションが落ちていくので、短い方がいいんです。
上手な人は「どこを大事にして、どこがざっくりしてもいいのか」を知っています。
及第点をクリアできるところから始まるので、あとは、好みにあわせて「テイクを選ぶ」をやっているだけです。
一番シンプルで、声の音色もニュアンスも最も良い選択をしています。
歌は「基礎力」が最も大事です。
基礎ができていれば「悪いところを直す」という作業が減っていきます。
悪いところがなくなれば「何が良いのか」が見えてきます。
「好きなものを選ぶ」がレコーディングの本質になります。
表現力もへったくれもなく「基礎ができていない」のが歌や発声のすべての原因の根源です。
まとめ
いやほんと、チートみたいに上手な人と会うと「人生って不条理だな」って思います(笑)
でも、この記事みたいにその内容を分析して真似をすれば、あなたもそのチートな要素を部分的に身につけられるかもしれませんよね?
すべてやり方次第です。
上手い人から上手に学んで、これであなたもチートシンガー!!!!!!